 テクニカルライティング
テクニカルライティング テクニカルライティング
はじめに 設計書というものを書く経験がなく、今回チャレンジさせてもらったが、書いたことないねと言われて、別の仕事をさせられた。そのときに、詳細設計書は、決められたフォーマットがあるが、その上の基本設計書になるとフォーマットとなる決められた...
 テクニカルライティング
テクニカルライティング 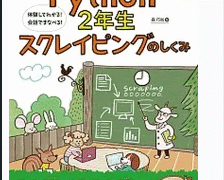 python
python 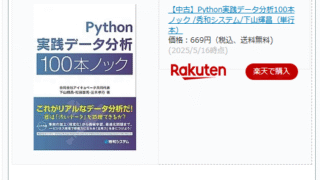 python
python 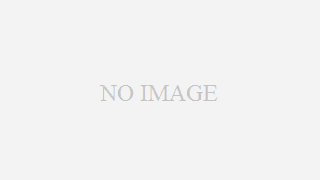 組込みエンジニアとしての活動
組込みエンジニアとしての活動 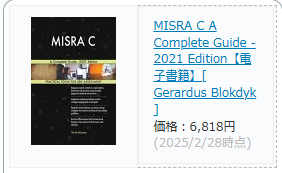 組込みエンジニアとしての活動
組込みエンジニアとしての活動 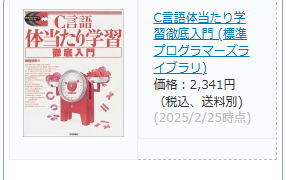 組込みエンジニアとしての活動
組込みエンジニアとしての活動 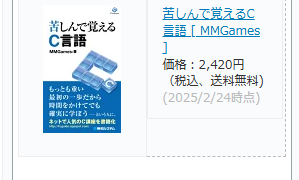 組込みエンジニアとしての活動
組込みエンジニアとしての活動 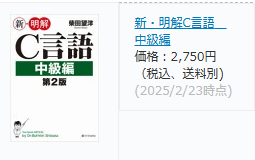 組込みエンジニアとしての活動
組込みエンジニアとしての活動 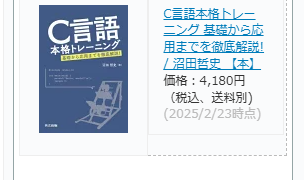 組込みエンジニアとしての活動
組込みエンジニアとしての活動 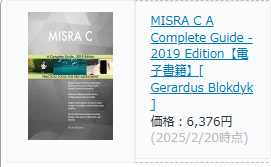 組込みエンジニアとしての活動
組込みエンジニアとしての活動